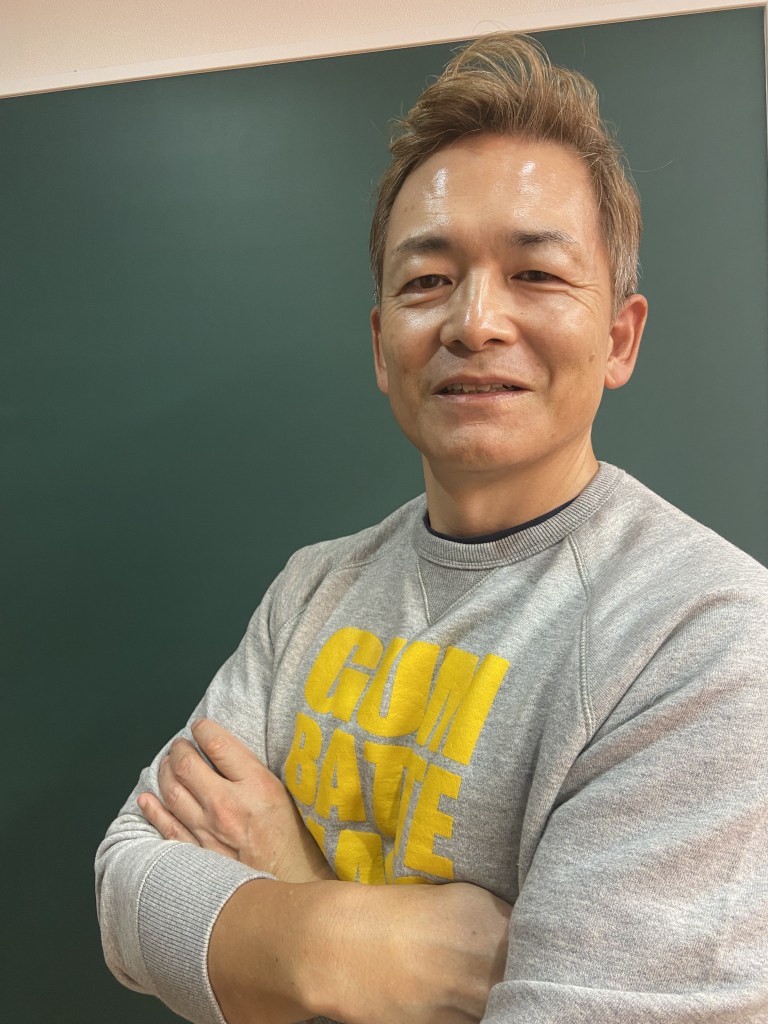池本克之です。
リーダーの中には、
「何か提案はないか?」
「意見がある人は何でも言ってくれ」
と言いながらも、
いざメンバーが発言すると、
その内容を一つひとつ丁寧に
論破してしまう人がいるようです。
なぜ、このようなことが
起こってしまうのでしょうか?
その理由の一つに、
「部下を教育するため」
という意識があることが挙げられます。
部下の発言に対して何かを言うことで、
指導や育成をしているつもりになって
しまっているのです。
そのため、部下の話を聴くというよりも、
発言の粗探しやダメな部分を見つけ出し、
「それは違う」と否定することに
なりがちです。
しかし、部下からすれば、
「話を聞いてもらえない…」
「何を言っても結局ダメ出しされる…」
と感じるようになり、
次第にやる気を失っていきます。
やる気がなくなれば、
仕事へのモチベーションは下がり、
仕事が他人事になってしまいます。
さらに、リーダーへの信頼も
薄れてしまうでしょう。
リーダーとしては、
よかれと思ってやっていることでも、
実はそれが部下との間に
大きな溝を作る原因になることも
十分にあり得ます。
部下との間に溝ができると、
「意見を言ってほしい」
「考えを聞かせてほしい」
と求めても、
誰も発言しなくなる可能性があります。
そうなると、
リーダーの期待する行動を
部下が取ってくれなくなり、
仕事の進捗も遅くなります。
結果として、お互いにストレスが増え、
組織がうまく機能しなくなるのです。
こうした状態を避けるためにも、
まずは部下の話をきちんと聴く
ことが大切です。
自分の考えをすぐに言いたくなっても、
まずはじっくりと話を聴く。
そして、一旦、
部下の意見を受け止めた上で、
もし別の考えがあれば、
それを伝えれば良いのです。
そうすれば、
部下も「自分の話を聴いてくれている」
と感じ、
「また話してみよう」と
思えるようになります。
さらに、このような積み重ねが、
リーダーへの信頼を深めることにも
繋がっていきます。
どんな人でも、
せっかく発言したことを
しっかり聴いてもらえなければ、
次からは発言を控えるように
なってしまいます。
お互いがストレスをためずに
仕事を進めていくためにも、
「聞いているつもり」ではなく、
「聴くこと」を意識する
このことを心がけていきたいものです。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら
池本克之です。
人間の感覚というものは、
あいまいで、人によって違うものです。
同じ言葉を使って伝えたつもりでも、
相手によっては違う受け取り方を
することがあります。
例えば、
「この資料をなるべく早くまとめて
おいてほしい」
と部下に頼んだとします。
そして、
「そろそろできているだろう」
と思い、進捗を確認すると、
「いえ、まだできていません…」
と言われたとき、
あなたはどう感じるでしょうか?
「え、まだできていないの?
早くと言ったじゃないか…」
と落胆するかもしれませんし、
「何でまだできていないんだ!」
と叱責したくなるかもしれません。
しかし、部下によっては、
「なるべく早く=明日まで」
と思う人もいれば、
「なるべく早く=1週間以内」
と考える人もいます。
そのため、たとえ上司に怒られたとしても、
「まだ2日しか経っていないのに…」
と思ってしまうのです。
このようなすれ違いが続けば、
お互いにストレスになり、
仕事もスムーズに進みません。
結果として、
お互いの関係性も悪くなってしまう
可能性があります。
では、どうすれば
こうした認識のズレをなくし、
ストレスなく仕事ができるように
なるのでしょうか?
その解決策の一つが、
「チェックリストを作ること」です。
チェックリストがあれば、
書いてあることをそのまま実行するだけなので、
指示の受け取り方の違いによるミスを
防ぎやすくなります。
また、書かれた内容が正解なので、
部下も安心して仕事を進めることができます。
チェックリストを作る際のポイントは、
1.期限(いつまでにやるのか)
2.内容(何をやるのか)
3.達成レベル(どのレベルまで仕上げるのか)
この3つを明確にすることです。
これが入っていれば、
どのような人が作業をしても
同じ結果を出せるようになるので、
安心して仕事を任せることができます。
そして、作成したチェックリストを使って、
「この仕事を任せる。
このチェックリストに書いてある内容を
この日のこの時間までに仕上げてほしい」
と具体的に伝えれば、
あとは途中で進捗を確認するだけで済みます。
人の感覚はそれぞれ違うものです。
その違いをできるだけ統一し、
お互いにストレスを抱えなくてもいいように、
「部下に頼んだ仕事が思うように進まない…」
「言いたいことがなかなか伝わらない…」
と悩んでいる人は、
ぜひ、今日ご紹介したチェックリストを
活用してみてください。
チェックリストを作るのは、
最初は手間に感じるかもしれませんが、
長い目で見れば、
お互いのストレスを減らし、
仕事の効率を上げる大きな効果を
もたらしてくれるでしょう。
池本克之です。
私たちは何かを始める時に、
目標を立てることが多い。
年初、または期のはじめに、
その年度の目標を決める。
新規受注数を前年比120%に設定する。
離職率を20%きることを目標にする。
など。
皆さんも過去にいくつもの目標を立てて、
それに向かって頑張った経験があるだろう。
だが果たして、その目標は達成できただろうか?
見事に達成した人もいるだろうが、
達成できなかった、という人も多いのではないだろうか。
「最初から無理のある数字だった」
「高望みだった」
理由は大体そんなところだろう。
そして、自分の能力のなさに落ち込んだり、
立てた目標そのものを否定したり、
その後の目標の修正に悩んだりする。
これは組織においても同様だ。
掲げられている目標が達成できないと、
全体の士気が下がってしまうことがある。
達成できなかった自分に自信がなくなり、
次の目標を見ても、意欲が沸かなかったり、
最初から消極的になってしまう。
さらに上司や社長から、
前回よりも高い目標を示されれば、
「前回達成できていないのだから、
今回だって無理に決まっているのに…」
「達成困難で現実離れした目標だ」
などど上司に対する不信感が生じ、
上司と部下の間に溝ができてしまう。
最初から諦めの気持ちがあるので、
モチベーションも当然低い。
パフォーマンスも落ちる。
これでは組織全体が
低迷してしまうだろう。
もちろん、目標は高く設定すべきだ。
だが、その高さの度合いが、
とても重要になってくる。
では、どの程度の目標を
掲げればよいのだろうか?
部下がモチベーションを保って、
前向きに達成を目指せるような、
理想の目標とは?
それは、
「背伸びをすれば手が届くかもしれない」
が高さの目標だ。
池本克之です。
部下のやる気を引き出すために、
見返りを与えているという人も
いるのではないでしょうか。
今の若い世代が
仕事に対するモチベーションを
失わないようにするためには、
相応の見返りが必要になります。
見返りには、さまざまな形があります。
例えば、給料やボーナスアップなどの
金銭的なものに限らず、
表彰制度や、
日常的なフィードバックなども
見返りに含まれます。
どのような見返りを与えるかは、
会社ごとに異なるかもしれませんが、
見返りを与える際に
絶対に注意しなければならないこと
があります。
それは、
一度決めた見返りの条件は
絶対に変更しないことです。
最初に決めた条件を、
合理的な理由もなく後から変更してしまうと、
部下からの信頼を一気に失います。
例えば、あなたが
「売上1000万円を達成したら
特別ボーナスを支給する」
と約束したとします。
しかし、売上1000万円を達成したにも関わらず、
「新規顧客の開拓が少なかったから、
あと3人新規顧客を獲得しないと
特別ボーナスは渡せない」
などと条件を後出しで付け加えるのは、
絶対にやってはいけません。
これをやると、部下からの信頼を
完全に失ってしまいます。
そして、部下との間に大きな溝ができ、
信頼を取り戻すのに
相当な時間がかかるようになるでしょう。
場合によっては、
二度と信頼を取り戻せないかもしれません。
「この人は信用できない」
と思われると、
部下の仕事の効率は落ち、
仕事のスピードも遅くなります。
また、仕事が他人事になり、
組織としての機能も低下してしまうでしょう。
これは、考えただけでも恐ろしいことです。
このような事態を防ぐためにも、
一度決めた見返りの条件は、
何があっても変えてはいけません。
これは、会社とスタッフが
交わした約束です。
会社の経営が悪化するといった
特別な事情がある場合は別ですが、
そうでない限り、
一度決めた約束は必ず守らなければならない
と肝に銘じてください。
あなたとスタッフが、
これからも長期的に
良い関係を築いていくためにも、
見返りを与えると決めた際には、
今日お話したポイントを
必ず守って実行してほしいと思います。
見返りがうまく機能すれば、
部下のモチベーションにつながり、
組織の成長スピードも加速するでしょう。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら
池本克之です。
働いている人の中には、
仕事を管理するのではなく、
人を管理している人が
まだまだ多いのではないでしょうか。
「そんなの当たり前じゃないか」
と思う人もいるかもしれませんが、
仕事ではなく人を管理していると、
組織の雰囲気が悪くなるだけでなく、
お互いの信頼関係までもが
崩れてしまう恐れがあります。
人を管理しなければと思っている人の中には、
部下が自分の考えた通りに
仕事を進めないと気が済まない、
という人が多いようです。
部下を疑い、警戒しながら
部下が作業をしている最中に
パソコンを覗き込み、
「ここの書式が違っているじゃないか」
と、細かくチェックを入れる人もいます。
こういった上司は、
部下にとってストレス以外の
何物でもありません。
常に監視されていると感じ、
気が休まらないだけでなく、
怒られるのではないかと怯えながら
仕事をするようになります。
こうなると、部下は自分の力を
最大限に発揮できなくなり、
ミスの原因にもなります。
また、このような状況に対して、
イライラを募らせる部下もいるでしょう。
「いい加減にしてくれよ」
と思いながら仕事をしていては、
やはり力を発揮できません。
上司としては、
「細かく指導したほうがミスを防げるから、
部下のためになる」
と考えているのかもしれませんが、
度を過ぎた指導は、
監視と同じレベルになってしまいます。
そうなれば、
部下の信頼を失うことにもつながります。
仕事を管理せずに、人を管理していると、
部下に出してほしい成果を
出してもらいにくくなるのです。
自分では良かれと思ってやっていても、
それが悪い結果を招くこともあります。
このような事態を避けるためには、
人を管理するのではなく、
仕事を管理することが重要です。
実際、僕自身も
部下を管理していませんし、
その必要もないと考えています。
仕事が計画通りに進んでいるかどうかが
わかれば、それで問題はないのです。
要所要所で進捗状況を報告させ、
仕事が順調に進んでいれば、
余計なことは言わずに
そのまま部下に任せています。
計画通りに進んでいない場合には、
詳細な打ち合わせを行い、
軌道修正のために、
ときには細かな指示を出すこともあります。
これが、「仕事を管理する」ということです。
仕事を管理せずに、人を管理してしまうと、
組織の雰囲気が悪くなるだけでなく、
出したい成果も出しにくくなります。
このような状況を防ぐためにも、
今一度、「自分は人を管理していなかったか?」
確認してみてほしいと思います。
それが、組織がうまく機能するための
大きなポイントになるのです。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら
池本克之です。
課題はなくならないものだと
私は思っている。
まして、経営者であれば
常に課題があるだろう。
しかし、中には課題が
ないという経営者がいる。
本当だろうか?
あり得るとすれば
1.課題という弱みを見せられない
2.変化から逃れ現状維持したい
3.現実を直視せず課題が発見できない
ということだろうか。
「課題がない」
そんなパーフェクトな会社が
あるだろうか?
日本で、世界で、実力のある会社が
たくさんあるが、どの会社も
課題があると言っている。
そうでなければ今以上の
成長はないだろう。
課題がある。山ほどある。
それを何とかして解決して、
もっと成長したい。
そういう経営者と私は仕事がしたい。
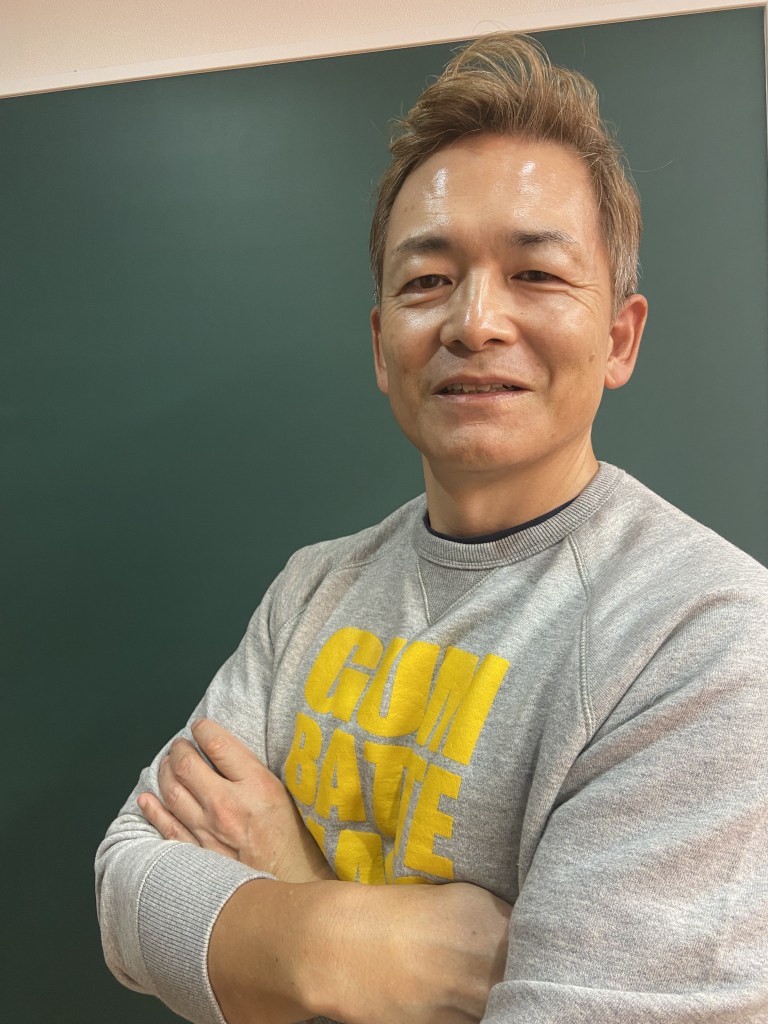
池本克之です。
人は、心を許している相手や
信頼している相手でなければ
本音を話すことはありません。
特に、上司と部下という関係においては、
部下が上司に対して本音を話すのは
簡単なことではないでしょう。
本音を言いたくても言えない人も
いるかもしれませんが、
「この人に話しても何も変わらない」
「言ったところで意味がない」
と思えば、話さなくなります。
このような状態が長く続くと、
仕事にも影響が出るようになります。
本音を言えないまま、
モヤモヤした気持ちが溜まり、
イライラが突然爆発することもあります。
そして、ある日突然、
「辞めます」となる人もいれば、
何の前触れもなく
会社に来なくなる人もいるでしょう。
また、本音が言えないことで、
仕事のスピードが遅くなり、
期待する成果が出せなくなったり、
成果を出すまでに時間がかかることもあります。
ただただ「やらされている」と感じるようになり、
仕事が他人事になってしまうこともあるでしょう。
このような状態を放置してしまうと、
組織としてうまく機能しなくなり、
会社の成長や売上にも
大きな影響を与えることになります。
では、どうすれば
部下が本音を話してくれるようになるのでしょうか?
部下の本音を引き出す秘訣とは何か?
それは、
「この人に話したい!」
「この人なら信頼できるから話してもいいかも…」
と、部下に思ってもらうことです。
人が本音を話そうと思うのは、
「自分の話をしっかり聴いてくれた」
と感じたときではないでしょうか?
しかし、多くの上司は、
自分の話ばかり一方的にして、
部下の話に耳を傾けることが
少ないように感じます。
正直なところ、
話を聞いてくれない上司の言うことなど、
誰も聞きたくありません。
賢い上司は、
自分から歩み寄り、
部下の声にきちんと耳を傾けるものです。
「自分の話を聴いてくれた」
「理解してくれた」
「受け止めてくれた」
このように感じてもらえれば、
部下はまた話そうと思えるようになります。
そして、このような積み重ねが
少しずつ信頼関係を築いていくのです。
部下は、本音を言わない、または言えないもの。
だからこそ、上司の方から歩み寄り、
部下の声に耳を傾けることが大切です。
少しずつでも信頼関係を築いていくことが、
部下の本音を引き出すカギになる
と僕は考えています。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら
池本克之です。
いまどきの若い部下が
何を考えているのかわからない…
何を望んでいるのかもわからない…
このように感じている人は
多いのではないでしょうか。
相手の考えや望みがわからないと、
こちらもどう対応したらよいのか
判断が難しくなりますし、
どのように接すればよいのかも
迷ってしまうことがあるでしょう。
また、どのような見返りを与えれば
モチベーションを高く維持しながら
働いてくれるのかも、
判断がつかないかもしれません。
このような状況が続くと、
お互いの関係性が悪くなる
可能性もあります。
関係性が悪くなれば、
仕事が進めにくくなり、
ずっとモヤモヤした気持ちを
抱えたままになってしまうかもしれません。
では、相手が何を考え、
何を望んでいるのかわからないときは
どうすればよいのでしょうか?
やはり、
「直接聞いてみる」ことが大切です。
例えば、
お金が欲しいと言う人もいるでしょうし、
時間が欲しい、
友達が欲しい、
と予想外の答えが返ってくることも
あるかもしれません。
ある会社では、
現金1万円を金一封として渡そうとしたところ、
「現金は生々しくて嫌なので、
受け取りたくない。
ただし、商品券ならOKです。」
という社員が少なくなかったそうです。
このような考えに
違和感を持つ人もいるかもしれませんが、
今の若者はこう考えているのです。
また、他にも
「ボーナスを人前で受け取るのは嫌だ」
という人もいるようです。
このとき、
「なぜ人前で受け取るのが嫌なの?」
と問い詰めても意味はありません。
嫌なものは嫌だからです。
それよりも、
「今の若者はこういう価値観なのだ」
と受け入れて、
相手が望むことや求めていることに
できるだけ応えるように努めることが
大切になります。
もちろん、一人ひとりの要望や要求に
完全に合わせるのは難しいかもしれません。
それでも、一律対応するよりは、
できるだけ個々の要望や要求に応えるほうが、
「この人は自分のことを
ちゃんとわかってくれている」
「理解してくれている」
と感じてもらいやすくなります。
また、相手が求めていることや
好きなもの、興味があることは、
普段の何気ない会話の中で
話していることが多いものです。
普段の会話の中から
相手の好みをリサーチし、
事前に準備しておくのも良い方法です。
これを読んでいる方の中には、
「そこまで気を遣わないといけないのか?」
と思う人もいるかもしれません。
しかし、今の若者をうまく動かすには、
こうした細やかな対応が不可欠なのです。
もし、あなたが
「今の若者が何を考えているのかわからない…」
「何を望んでいるのかわからない…」
と感じているのであれば、
ぜひ直接本人に聞いてみることを
オススメします。
相手のことがわかれば、
こちらができることも見えてきますし、
お互いの関係性もより良くなっていくでしょう。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら
池本克之です。
これまでに何度かお話しているが、
「部下に言ってはいけない一言」
というものがある。
その一言で
部下のモチベーションは
一気に下がってしまう。
これからお話しするその禁句、
部下のモチベーションを下げる一言とは、
「自分で考えろ」
という言葉だ。
いまどきの若い世代は、
この言葉を投げられると、
一瞬で心が折れてしまう。
この言葉のもつ破壊力は、
計り知れないほど大きいものだ。
いまの若い人たちは
自分を出すことに臆病だ。
人に些細なことを聞くだけでも
相手の反応を気にして不安を抱いてしまう。
「いま話しかけて平気だろうか?」
「こんなこと聞いていいのかな…」
「迷惑なヤツと思われるかも…」
そんな彼らが、やっとの思いで、
勇気を振り絞って上司の意見を求めたときに
「それぐらい、自分で考えろ」
と言われたら、
もう二度と質問などできなくなるだろう。
怒られたと感じる人もいるだろうし、
低レベルの質問をしてしまったのか?と、
後悔し、落ち込む人もいるだろう。
そして、自分に自信が持てなくなり、
かと言ってまた質問することもできず、
悶々としながら過ごすことになる。
こうなると、負の連鎖が始まってしまう。
自分に自信がないため、
仕事でも自分の能力を存分に発揮できなくなる。
上司だけでなく、
他のスタッフとの意見交換にも、
消極的になってしまう。
周りとのコミュニケーションが薄れ、
わからないことを誰にも聞けず、
一人、孤立状態となる。
そしてある時、
「辞めたい…」と思うようになるのだ。
せっかく志をもって入った会社で、
自分の能力を十分に発揮できないのは、
とても勿体ないし、不幸なことだ。
聞く機会を奪われることで、
本人の成長する機会までも、
失われてしまうのだ。
もしそのような精神状態で仕事を続けていれば、
仕事の生産性や精度は落ち、
結果的に会社全体に影響を及ぼしてしまう。
本人にとっても不本意だろうが、
会社にとっても同じだろう。
このような事態を生まないために、
上司は、
上の「禁句」を心得ておくべきだ。
部下からのどのような疑問にも応え、
小さなことでも教え、そして見守る。
言われたことを覚え、経験を重ねる中で、
やがて部下にも自信が生まれ、
自分で考えて行動できるようになるだろう。
私たちが若かった頃と時代は変わっている。
これからの会社の成長を担っていく若者たちを、
生かすも殺すも上司次第だろう。
成長する芽を摘まないことが、
とても大切だと感じている。

池本克之です。
あなたは、
「採用に失敗したな…」
「間違ったかな…」
と思った経験はないでしょうか?
きっと、多くの社長が
人材採用の失敗を経験しているでしょう。
実は、私自身も経験があります。
以前、私がある会社の経営者を
していたとき、
その会社は短期間で急成長しました。
その結果、
今までは自分で何でもかんでも
やっていましたが、
身が持たないほどの仕事量を
抱えることになったのです。
そんなときに、
「人を採用して、少しずつ仕事を
任せていくしかない」と考えました。
しかし、
慌ててスタッフを採用したため、
見込み違いの人を雇ってしまった
ことがありました。
例えば、
私が指示したことを
やってくれなかったり、
他の人と反りが合わなかったり。
その結果、
スタッフ同士の揉め事が増え、
私はその火消しに
多くの時間を取られることになりました。
このとき、
私は「失敗したな…」
と強く感じたのです。
私自身、このような経験がありますが、
「採用した人が、自分が思っていたような人と違った…」
と感じた経験がある人は多いのではないでしょうか?
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
なぜ、採用の時点で気づくことができなかったのでしょうか?
もし、採用の時点で気づけていれば、
後々起こるかもしれないトラブルや問題を
事前に回避できたはずです。
それに、無駄な時間やお金を
費やさずに済んだかもしれません。
採用の失敗の原因の1つは、
「社長の価値観が明確になっていない」
ということにあると考えています。
-あなたの会社に合った人とは、どのような人か?
-あなたの会社に必要な人材は、どんな人か?
これらを明確にすることは
とても重要であり、
これが「採用基準」になります。
採用基準がないと、
間違った人を採用しやすくなります。
そして、
間違った人を採用してしまうと、
後々トラブルの原因になりやすいのです。
それに、せっかく採用したのに
適性が合わなければ、
また新しい人を採用し直すことになり、
お金も時間も無駄になってしまいます。
「人を採用すれば、自分が楽になる」と
思っていたのに、
実際には何も変わらない…
それどころか、
以前よりも自分の時間が取られるようになった…
なんてことになれば、それは悪夢です。
このような状況を避けるためにも、
そして何度も採用に失敗しないためにも、
「採用基準」を作ることは、
社長の急務だと考えています。
採用基準があれば、
それをスタッフにも共有することで、
スタッフ自身も
「この人は、自社に合っているのかな?」
と判断できるようになります。
そうすれば、あなたと同じ目線で
採用を考えられるようになるのです。
もし、あなたが思っていたような人とは
違う人材を採用してしまったら、
せっかく投資したお金・時間・労力までもが
無駄になる可能性があります。
このような事態を防ぎ、
自社に合った人材を採用し、
長く働いてもらうためにも、
あなたの価値観を明確にし、
採用基準を作ることをオススメします。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら