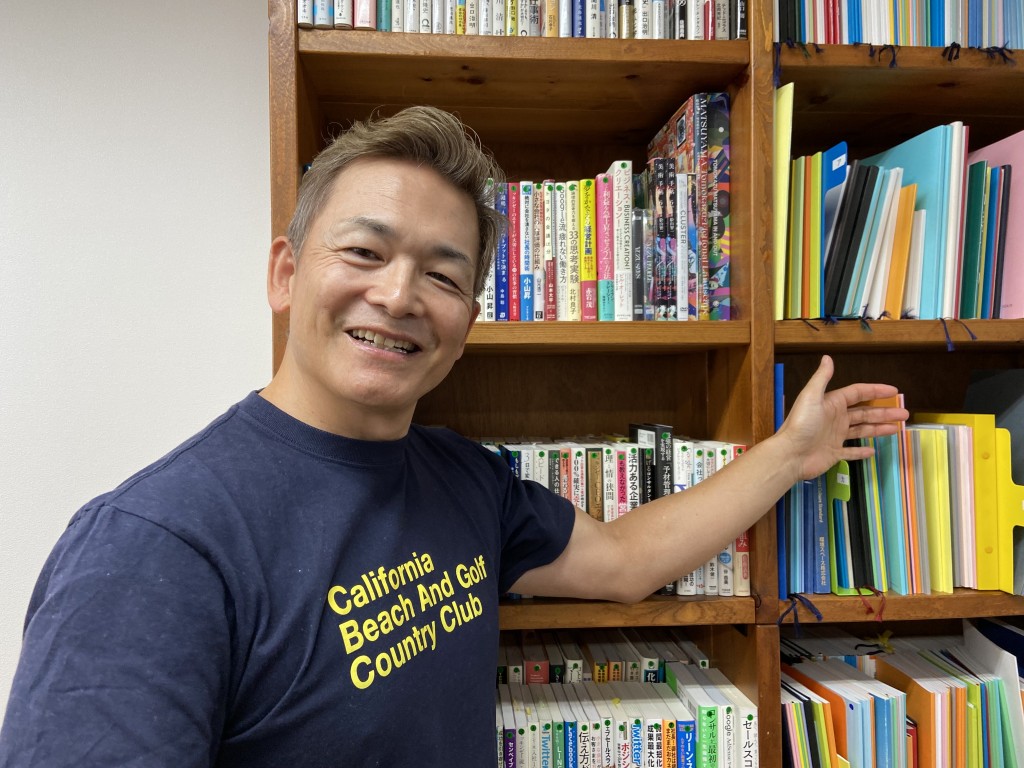池本克之です。
組織にいる一人ひとりの
生産性をもっと上げたいと
思っている社長さんは、
きっと多いのではないでしょうか。
一人ひとりの生産性が上がれば、
仕事が終わるスピードも早くなり、
今よりも効率よく進めることが
できるようになります。
そうなることで、
ストレスを感じる時間も減り、
気持ちに余裕を持って
仕事に向き合えるように
なるかもしれません。
これは、すごくいい状態ですよね。
仕事なので、
ストレスがゼロというわけには
いきませんが、
生産性が上がれば、
イライラの時間も減ってきます。
そんな生産性アップの方法として、
「ブラックボックスの仕事をつくらない」
という考え方があります。
ブラックボックスの仕事とは、
「その人にしかできない仕事」のこと。
もし、その人が休んだり
退職したりしたら、
現場は混乱してしまいます。
なぜなら、
その仕事のやり方が
誰にも共有されていないからです。
それでは困りますよね。
お客様に迷惑をかけることにも
つながってしまいます。
だからこそ、
「誰かにしかできない仕事」
をつくらないことが大事なんです。
とはいえ、そう言うと
「それは嫌だ」と感じる人も
いるかもしれません。
例えば、ナンバー1の営業マン。
契約のとり方や
独自の人脈などを
他の人に知られたくない、
という気持ちもあるでしょう。
もし教えたら、
自分がナンバー1で
なくなるかもしれない。
でも、その人が
いなくなってしまったとしたら、
会社にとっては大きな損失です。
だから、ナンバー1営業マンの
ノウハウをマニュアル化して
共有しておくことが必要なんです。
もし本人が抵抗するなら、
「じゃあ、あなたが教えてあげて。
教えた人がナンバー1になったら
同じ報酬を出すよ」
といったかたちで説得してみましょう。
もちろん、ノウハウを真似したからといって
誰もがナンバー1になれるとは限りません。
でも、今まで月に2〜3件しか
契約できなかった営業マンが、
5〜6件とれるようになるだけでも
大きな変化です。
会社の売上も上がるでしょうし、
本人の自信にもつながります。
つまり、たとえ優秀な社員がいなくなっても、
会社の売上が落ちず、
現場も混乱せずに回るように
しておくことが大事なのです。
そのためにも、
ノウハウを社内で共有しておくことが
とても大切です。
これができるようになると、
会社の成長スピードは上がり、
組織の生産性も確実に
高まっていくでしょう。
池本克之です。
皆さんは
「技術を目で盗む」
「背中で語る」
「身体で覚える」
などの表現を聞いたことがあるだろうか。
仕事やものごとの教え方、学び方の、
一種のスタイルを表した言葉で、
職人の世界でよく使われる。
巧みな職人技は、
文字や言葉による説明では
表現しきれない。
師匠の息遣いや
道具の絶妙な使い方など、
五感で修得するしかないのだろう。
ところで、私たちの仕事はどうだろう?
経営者や社長、上司は、
「師匠」や「親方」と同じだろうか?
そして、部下は「弟子」のようなものだろうか?
当然ながら、
答えは「ノー」だ。
会社のトップは、その組織の目標を掲げ、
理念に基づいて、成果を上げていくために、
スタッフたちを上手に采配するのが務めだ。
それなのに、
「仕事は見て覚えろ!」
「とにかくやってみろ!」
と部下に対していう人がいる。
まるで一昔前の会社だ。
年功序列が当たり前だった頃は、
そのような風潮も当然多かっただろう。
どんなに能力のある部下でも、
仕事を説明してもらえなければ、
能力を発揮することはできない。
上司の座は安泰、というわけだ。
部下は、その仕事がわかるまでに、
相当な時間を費やすことになる。
見よう見まねでできる仕事には限度があり、
単純作業の延長に過ぎないだろう。
仕事のヴィジョンがわからなければ、
具体的な方向性が見いだせず、
効率も生産性も落ちてしまう。
目的も、全体像もつかめないまま、
上司の背中だけを見て仕事を続けていては、
部下のモチベーションは下がる一方だ。
説明や教えを求めても
「何度も言わせるな!」
「見ててわからないのか?」
などと叱責されれば、
能力のある部下も、
自信を持てなくなるだろう。
これでは、
組織の成長や発展は望めないし、
可能性を秘めた若い部下を、
つぶしてしまうことにもなる。
良いことは一つもない。
最近の若い人たちに、
昭和の「根性論」はナンセンスだ。
彼らは子供のころから、
丁寧に、一人一人に合わせて、
ものごとを教わり、学んできている。
言われたことはよく守る。
テキストやマニュアルがあれば、
その通りに行うことは得意だ。
人前で発言するのは苦手なので、
わからないことがあっても、
なかなか質問できない。
目標を与えられれば、
真面目に取り組んで達成する。
褒められると安心する。
そんな今どきの部下たちの特性を、
上司がしっかり理解していれば、
彼らの持つ能力を、
最大限に引き出すことができるだろう。
一人一人が躓かないように、
最初に懇切丁寧に教えることが肝心だ。
やるべきこと、目標がわかれば、
彼らは真面目に取り組むだろう。
疑問や悩みはいつでも相談できるような、
職場環境を整えておくことも大切だ。
私達の仕事は、
背中で語ることが難しい。
声に出し、文字に起こして、
社長として教えたいことを示すことが必要。
そうすれば組織の価値観は共有され、
若い部下も自信をもって活躍できるだろう。
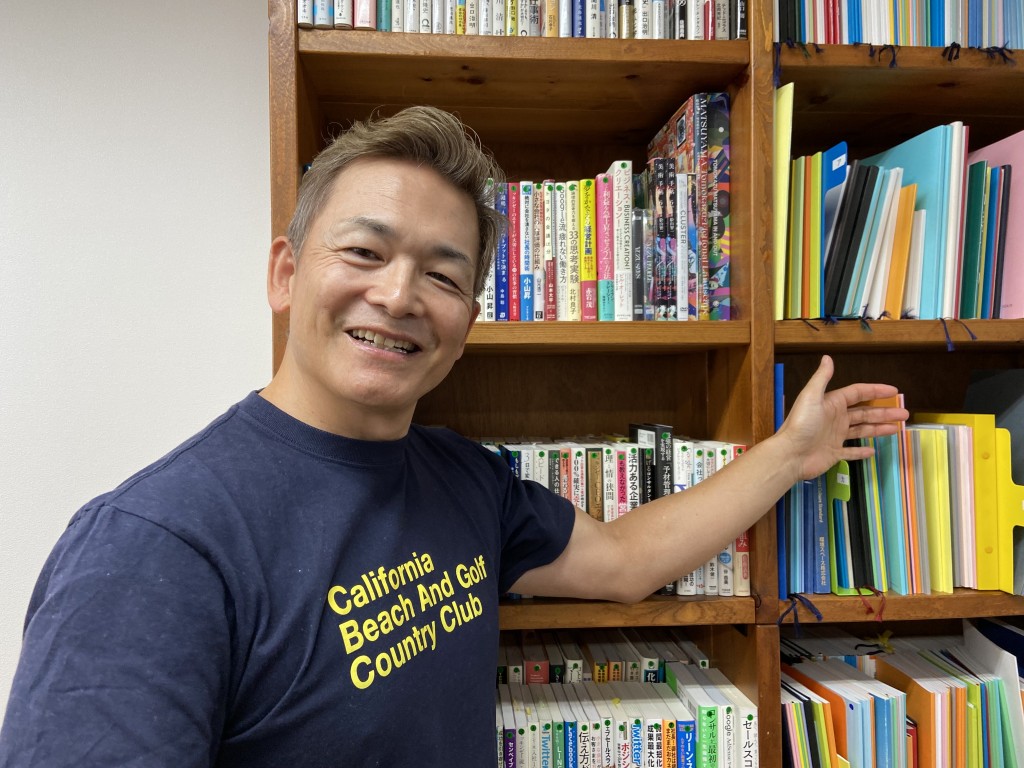
池本克之です。
私はゴルフが好きなのですが、
ゴルフをされる方の中には、
いまいち調子が上がらないと
「今日はやーめた」と言って、
適当に打ち始めてしまう方がいます。
まあ、ミスショットばかりが続くと、
そういうお気持ちもわからなくはありません。
また、ゴルフ以外にもテニスなどのスポーツで、
劣勢になって大差がついてしまうと、
試合の途中で
「どうせ勝てない…」
「もういいや…」
と思い、無気力になってしまう方もいます。
確かに、相手にだいぶリードされていたり、
うまくいかないことが続いてしまうと
「もういいや」と思う気持ちも、
理解できなくはないです。
でも、そういう方をみると
「その発想を仕事にも持ち込むのですか?」
と聞きたくなります。
「仕事にも同じ態度で臨まれるのですか?」
「業績が伸びなければ
“この会社はもういいや”と
経営を放り出すのですか?」
と聞きたくなってしまうんです。
こんなお話をすると、
「いやいや、仕事ならそんなことはしないよ」
と言う方もいるかもしれません。
「もちろん、仕事は本気でやるよ」
と答えられるかもしれません。
仕事と遊びは別だから、と。
ですが、実際はどうでしょうか。
好きな遊びですら、
調子が悪いとすぐに諦めてしまう方が、
決して楽しいばかりではない仕事に対して、
何があっても粘り強く取り組めるとは思えないんです。
事実、そういう方でビジネスにおいて
大きな成果を上げている方を、
私は知りません。
「遊びだからどうでもいい」
「遊びだから支障はない」
と思って途中で投げ出していると、
実際のビジネスの場面でも
同じ思考のクセが出やすくなります。
うまくいかないとすぐ諦めたり、
自分の思い通りに進まないと、
すぐにモチベーションが下がってしまう
考え方になりがちです。
では、思考のクセは直せないのか
といえば、そんなことはありません。
トレーニング次第で、
より良い思考のクセを
身につけることはできるんです。
その思考のクセは、
普段の遊びのときから意識しておくと
身につきやすいのです。
たとえば、私はゴルフ以外に
マラソンも好きなのですが、
ウルトラマラソンを走るときは、
70km付近になると
毎回ものすごくきつくなってきます。
体からも悲鳴が聞こえてくるような状態です。
ここで「やーめた」とリタイアするのは、
とても簡単ですし楽でもあります。
でも、ここまで準備して、
ここまで走ってきた積み重ねが、
そこで終わってしまうんですよね。
そんなときこそ、
「タイムが振るわなくても、
完走という大きなゴールが
待っているじゃないか」
と、無理やりにでも思考を
そちらの方向に持っていくんです。
その結果、完走した人でなければわからない
圧倒的な達成感を味わうことができます。
(本当に最高の気分です)
私の場合はマラソンですが、
どんな趣味や遊びでも
真剣に取り組んでいれば、
同じようなトレーニングの機会は
必ずあると思います。
どんなに苦しくても諦めない、
という思考のクセがつけば、
それは必ずビジネスにも生きてきます。
大切なときに逃げ出さないためにも、
そして重要な場面で決して諦めないためにも、
普段から思考のクセを意識して
過ごしていきたいですね。
池本克之です。
日本では、ダラダラと
長い会議を行う会社が
非常に多いと感じております。
会議には、参加者の人件費、
光熱費、設備、備品など
実はさまざまなコストが
発生しております。
それにもかかわらず、
ダラダラとした会議を続けるのは
非常に非効率であり、
時間の浪費にもつながります。
当然、生産性も
極めて低くなるでしょう。
長時間会議をして
結論が出るならば
まだ良いかもしれませんが、
どれだけ時間をかけても
結論が出ないこともあります。
さらに、参加者のモチベーションが低く、
発言もほとんどない会議も
少なくありません。
なぜ、このようなことが
起こってしまうのでしょうか。
どうして、これほど多くの時間を使っても
結論が出せないのでしょうか。
原因はさまざま考えられますが、
その一つに「時間を決めていない」
という点があると私は感じています。
時間の設定がないことにより、
会議がダラダラと長引き、
結果として全員のモチベーションが
下がってしまいます。
一般的に、人間の集中力は
およそ50分が限界と言われています。
つまり、会議が50分や1時間を超えると
集中力が途切れ、
目に見えない損失が
発生しているのです。
このような状況では
生産性の高い会議には
なりません。
では、どうすれば良いのか。
大切な時間を無駄にしないための
工夫が必要です。
私が実践している方法の一つに
「時報を鳴らす」
というものがあります。
会議の際、タイマーをセットし、
30分おきにアラームが鳴るように
設定します。
今では、スマートフォンの
時間管理アプリを使えば
簡単に実現できます。
途中でアラームが鳴ることで、
「もう30分経ったのか」と
気づくことができ、
会議の流れがリセットされ、
再び集中を取り戻せるのです。
また、会議の延長を避けると決めれば、
全員が限られた時間内で
効率的に議論を進めるようになります。
会議には、人件費、光熱費、
設備や備品など、
多くのコストがかかっております。
時間をかけたにもかかわらず、
「何も決まらなかった」
「結局、何の会議だったのか分からない」
という状況にならないためにも、
時報を活用することを
おすすめいたします。
それが結果として、
会議の生産性を高め、
効率の良い意思決定に
つながるのです。
池本克之です。
誰でも1日24時間しかない。
やれることには限りがあるし、
どれだけ時間を有効に使えるかで
結果も変わってくる。
社長は時間をとても大事にする。
社長は常に仕事に追われており、
会社の中だけでなく、外の世界にも
出ていかないと、人の出会いも
拡がらなくなるため、会合にも時間を使う。
例えば、会社で仕事に集中していても
部下から質問があったり、
電話がかかってきたり、
突然、誰かが訪ねてくる
なんてこともある。
気付かないうちに色々なところで
時間は奪われているものだ。
会社を成長させていこうと思えば、
少しの時間もムダにはしたくないし、
何でも効率良くやりたいとも思うだろう。
効率良く仕事ができることは
重要で、次の仕事にスムーズに取り掛かれるし、
自分の気持ちにも余裕が生まれるようになる。
気持ちに余裕が生まれれば、
やらなければならないことに
より集中できるようにもなる。
弊社では「集中タイム」という、
この1時間は誰にも話しかけてはいけない、という
時間を設定している。
一番、生産性の高く、集中できる
午前中10時から11時まで。
この時間内にかかってきた電話は、
係の人が電話に出て、
用事がある人に代わることなく、
後ほど折り返す、ということで
対応している。
ほとんど緊急の用件はないので、
何も問題は起きない。
この時間の使い方は、お客様にも
よくおススメしている。
社長、社長にとっても時間は貴重なものだし、
決してムダにはしたくないものだ。
ぜひ時間について、
一度考える時間をもってほしい。

池本克之です。
始めて「ビジョナリーカンパニー②」を
読んだときに引いたアンダーラインが
色褪せてしまっている。
しかし、リーダーの特徴として
二面性があることについて書かれた
部分は鮮明に焼き付いている。
「個人としての謙虚さ」と
「職業人としての意志の強さ」という一見
矛盾する「二面性」を兼ね備えている。
さらに、飛躍した偉大な企業に共通する
企業理念として、次のようなことも
言っている。
自社の基本理念という一貫性を維持しながら、
同時に常に変化し続けて進歩し続けるという
矛盾する「二面性」も兼ね備えている。
チームビルディングをコンサルティングする
うえで、この矛盾する「二面性」を企業文化に
することを強く進めてきた。
この「二面性」を見事に
表現している人物がいる。
現代芸術家の松山智一さんだ。
https://www.tomokazu-matsuyama-firstlast.jp/about.html
ちょうど今、東京の麻布台ヒルズで
開催されている個展の特設サイトで
こう紹介されている。
アジアとヨーロッパ、古代と現代、具象と抽象
といった両極の要素を有機的に結びつけて再構築し、
異文化間での自身の経験や情報化の中で移ろう
現代社会の姿を反映した作品を制作する。
異なる要素が融合するとはどういうことなのか?
ビジネスばかりではなく、芸術という異なる
観点からもリーダーの在り方、偉大な企業の
共通点を感じ取れる。
あなたの矛盾する「二面性」は何だろうか?
それが最後に残る本質になるはずだ。

池本克之です。
大きな問題を見つけるのは簡単ですが、
小さな問題を見つけるのは意外と難しいものです。
以前、僕の会社でオフィスの
観葉植物が枯れかけていたことがありました。
しかし、これだけなら大きな問題ではありません。
それとは反対に、
「お客様からクレームがきた!」
というようなことであれば、すぐに気づきますし、
誰もが「何とかしないと!」と思うでしょう。
クレームは放置できないため、
すぐに対策を考えるはずです。
しかし、オフィスの観葉植物が枯れていたり、
小さなゴミが落ちている程度では、
それを問題と考える人は少ないかもしれません。
「後回しでもいいか」と思い、
そのまま放置されることもあるでしょう。
ですが、実はこうした小さな問題が
会社に悪影響を与えることもあります。
例えば、僕の会社には
クライアント様が訪れることが多いので、
枯れた植物を見たら
「この会社、大丈夫かな?」
と思われるかもしれません。
また、
「何だかみすぼらしく見えるな…」
と感じる人もいるでしょう。
こうした印象は、
会社にとっての損失につながります。
観葉植物の管理は業務とは
関係ないと思うかもしれませんが、
実はこれも大切な仕事のひとつなのです。
僕ら経営者は、自分の会社に
ゴミが落ちていたらすぐに拾いますし、
観葉植物が枯れていたら気になります。
それが良くないこと、
会社にとってマイナスだとわかっているからです。
しかし、スタッフにとっては、
それが会社に損害を与えるとは思えませんし、
そもそも問題だとも認識していないことが多いのです。
そのため、放置されてしまったり、
すぐに行動に移すことができないのです。
では、どうすればよいのでしょうか?
それは、
「なぜ、それをしなければならないのか?」
「なぜ、それが大事なのか?」
をしっかり説明することです。
僕の場合、観葉植物に水をあげることの意味を、
仕事の全体像と関連づけてスタッフに説明しました。
水やりをするのは、僕のためではありません。
しかし、もしオフィスが汚いという理由で
クライアント様が離れてしまえば、
会社の売上が減り、最終的には
スタッフの給料も支払えなくなります。
だから、オフィスの掃除も、水やりも、
壊れたものを取り替えることも、
大切な仕事の一部なのです。
そう説明すると、スタッフも納得し、
交代で水やりをするようになりました。
これは、小さな問題にスタッフが
気づけるようになったからこそ、起こった変化です。
もちろん、一度説明しただけでは
忘れてしまうこともあります。
だからこそ、メンバー全員の意識が揃うまで、
何度でも伝え続けることが大切です。
組織のメンバー一人ひとりが、
仕事の中で起こる小さな問題に
気づけるようになれば、それは確実に
会社の成長へとつながります。
一日でも早く、あなたの目指す
ゴールに到達するためにも、
小さな問題にこそ意識を向けられるように、
教育していくことがとても重要ではないでしょうか。
池本克之です。
上司の中には、
部下に嫌われたくないという理由で
仕事を任せない人がいるようです。
どういうことかというと、
ちょっと部下が忙しそうにしているのを見ると、
何か依頼したい仕事があっても
「任せるのは悪いな…」
と思い、すべて自分で背負ってしまう、
ということです。
「今、仕事を任せたら、
また〇〇さんが仕事を持ってきた…
勘弁してくれよ、と思われるかもしれない」
「そう思われたら嫌だな…」
と、心理的に躊躇してしまうのです。
人は、他人から嫌われたり
批判されることを恐れるものです。
しかし、そうすると上司の仕事がどんどん増え、
本来やるべき業務があるにも関わらず、
部下の仕事まで抱えてしまうため、
結果的に1人だけが大変になってしまいます。
仕事に追われることで、
ストレスがたまりやすくなります。
ストレスがたまると、
イライラしやすくなることもありますし、
逆にモチベーションが一気に下がって
燃え尽き症候群のようになってしまう人も
いるかもしれません。
もしそうなってしまったら、
上司が倒れた瞬間に仕事が止まってしまいます。
結局、その仕事は誰かが引き継がなければならず、
負担が他の誰かにのしかかることになります。
これは悪循環です。
さらに、上司の「部下に嫌われたくない」
という考えは、部下自身にも悪影響を与えます。
仕事を任せないことで、
上司の能力ばかりが伸びてしまい、
部下の成長が止まってしまうからです。
これでは、部下が成長する機会を失ってしまいます。
上司が持つ「部下に嫌われたくない」という考えは、
一旦脇に置く必要があります。
とはいえ、部下が大変そうにしていると、多くの人が
「今は仕事を任せられないな…悪いよな…」
と思うかもしれません。
「こんなタイミングでお願いしたら、
嫌われるかもしれないな…」
と気にする人もいるでしょう。
では、どうすればいいのでしょうか?
たとえ部下に「忙しいのに」と嫌がられたとしても、
会社のためには仕事を任せるしかないのです。
「えっ?」と思う人もいるかもしれませんし、
少し厳しく聞こえるかもしれません。
しかし、上司の給料には、部下に仕事を任せ、
動かし、成長させる業務に対する対価も含まれている、
ということを決して忘れてはなりません。
とはいえ、部下が本当に大変そうなときは、
どうすればスムーズに仕事を進められるかを
一緒に考えて進めていくのもよいでしょう。
上司の「部下から嫌われたくない」という気持ちが、
部下の成長機会を奪わないようにするためにも、
僕自身も含め、意識して仕事をしていきたいものです。
池本克之です。
私たちはこれまでの人生、
それぞれ違う環境で生きてきた。
同じ日本の、同じ都市であっても、
それぞれの居た地域、育った家庭、
通った学校、周りの友達、などによって、
形成される感覚もかなり違ってくる。
また、「甘味」「苦味」「辛味」など、
味覚の度合いが人によってかなり違うことは、
皆さんもよく経験するだろう。
何気ない会話から、
お互いの感覚の違いを知ることは、
興味深く、面白いことかもしれない。
だがそれが、ビジネスの場面となると、
面白い、などと言ってはいられない。
「このデータ、なるべく早く、見やすい形にまとめておいて」
と、上司が部下に依頼したとする。
このとき上司は、自分の頭の中で、
「今日中は無理でも明日には、〇枚くらいのシートで、
こんなイメージでまとめてくれるだろう」
などと、自分なりに予想をしているだろう。
一方、頼まれた部下の方はと言えば、
他の仕事もこなしつつ、時間を割いて、
自分のやりやすい方法で、何日か後に、
それなりのものを作成するつもりでいるかもしれない。
やがて、上司が「そろそろかな?」と、
部下にその進捗を尋ねたとき、
まだ全くできていなかったとしよう。
それぞれ、どう思うだろうか?
上司は
「頼んでから十分な時間が経っているのに、
まだできていないなんて、遅い!」
と腹立たしさや怒りを感じるだろう。
部下は部下で
「まだそんなに時間も経ってないし、
他の仕事もあるんだから、できてなくて当然だろう」
と不本意に思うに違いない。
或いは、作業は終わっていたが、
できあがったものが、上司のイメージと違うものかもしれない。
この場合も、上司は落胆することになるだろう。
「なるべく早く」「見やすい形で」
という曖昧な表現だったために、
それぞれの感覚で捉えた結果、ズレが生じたのだ。
このような感覚や認識のズレは、
仕事上の大きなエラーに繋がる危険性がある。
そして、何より、お互いの感情面にマイナスとなり、
関係性が悪くなってしまうだろう。
人間関係のストレスがあると、
組織全体の雰囲気も曇ってしまう。
このような感覚のズレを解消し、
お互いがストレスなく仕事を進めるために、
よい方策があるので、紹介しよう。
それは至ってシンプルで、
「チェックリストを作る」
ということだ。
チェックリストに書かれた内容を、
皆が確認し、共有し、実践する。
ただし、
そのチェックリストの内容が曖昧であっては無意味だ。
効果的なチェックリストを作成する必要がある。
チェックリストの項目のポイントは3つ。
「期限」「内容」「達成すべきレベル」
この3つに曖昧さがあってはならない。
つまり、この3要素が具体的で明確であれば、
認識のズレが起こりにくく、
間違いが起こる可能性が、極めて低くなるのだ。
3要素が的確に示されたチェックリストを用いれば、
依頼された仕事の期限も内容もクオリティも、
視覚化された文字情報として認識できる。
誰が見ても内容が明確であるから、
進捗管理もしやすく、ストレスがかからない。
リストを作るより、口頭で指示したほうが楽だ、
こう思う人もいるかもしれない。
だが、
「部下が思ったような仕事をしてくれない…」
「言いたいことが上手く伝わらない…」
と悩んでいる人の原因は、そこにあるのかもしれない。
チェックリストを作るという、たった「ひと手間」が、
ストレスのない仕事環境への第一歩だとしたら、
やらない手はないだろう。
上司である人のためにも、
部下である人のためにも、
チェックリストの作成と活用は、有効だ。
是非、あなたの職場で試していただきたい。

池本克之です。
上司の中には、自分の考えを
部下に押し付けようとする
人もいるのではないでしょうか。
例えば、
「俺は、このやり方でやってきた。
だから、お前もこれでやれ」
「謝罪は直接会って行うのが常識だろう」
「電話やメールよりも会いに行け!
俺はそうしてきたんだ」
といった言葉です。
言っている本人には、
自分の考えを押し付けているという
意識はないのかもしれません。
しかし、部下の立場からすると、
上司のやり方を押し付けられているように感じたり、
強制されていると思ってしまい、
嫌な気持ちになることがあります。
「それは、〇〇さんのやり方であって、
自分には合わない」
そう思う人もいるでしょう。
また、自分の考えとは違うことを
押し付けられていると感じると、
行動に移すまでに時間がかかったり、
モチベーションが下がる原因にもなります。
これでは、部下に長期的に
成果を出し続けてもらうのは難しくなってしまいます。
では、どうすればスムーズに動いてもらえるのでしょうか?
それには、まず
「本人にとってやりやすい方法で行動してもらう」
ことが大切です。
ベテラン上司の中には、
「謝罪は直接会って行うのが常識だ」
と言う人も多いかもしれません。
しかし、今の若い世代にとっては、
メールやSNSでのやり取りが当たり前です。
人によっては、メールの方が上手に謝罪できたり、
気持ちを伝えやすいと感じる場合もあります。
また、謝罪を受ける相手も若い世代であれば、
むしろメールの方が好ましいと感じるかもしれません。
一方的に「これが正しい」と
やり方を押し付けるのではなく、
まずは本人がやりやすい方法で行動してもらう。
そして、部下から相談されたときには、
「僕はいつもこんなやり方でやっているよ」
と、自分の方法を伝えるのがよいでしょう。
そうすることで、部下自身が
「そんなやり方もあるのか」と考えるきっかけになります。
自分のやり方を押し付けるようなコミュニケーションは、
部下のモチベーションを下げる大きな原因になります。
そうならないためにも、部下に選択肢を与え、
自分で考えさせるようなコミュニケーションを
取ることがとても重要だと感じています。