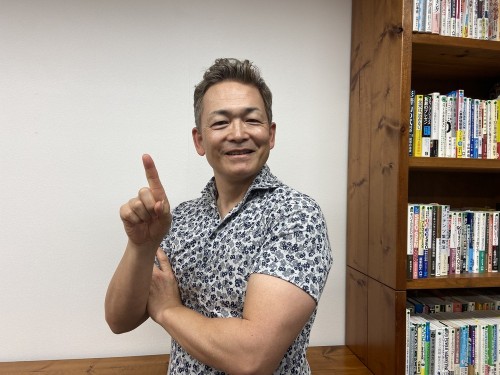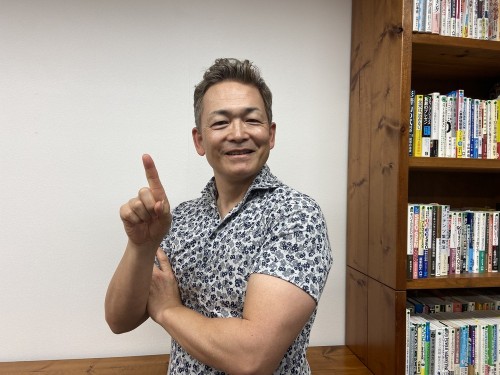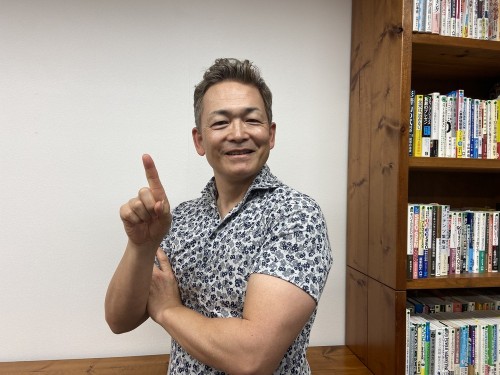池本克之です。
多くの経営者が知る名著
「ビジョナリー・カンパニー2
飛躍の法則」にこんな記述がある。
“偉大な企業の経営者は、まずバスの
行先を決め、それからバスに乗る人を
決めるのではない。
適切な人をバスに乗せて、ふさわしい席
に着かせ、不適切な人をバスから降ろすと
バスは素晴らしい場所に行ける”
人事管理をバスにたとえ
「誰を乗せて、誰を降ろすのか」
を決めるのが優先課題だと言っている。
これは、とても重要な考え方だ。
自社に合わない人がバスに乗っていると
目指している場所に行きにくくなる。
協力をしないどころか邪魔をするから。
そうならないためには、
まずは誰と行くのかを決める
必要があるのだ。
つまり、組織づくりをするうえで
最も重要なプロセスは採用である。
誰をバスに乗せるかで行き先が決まる。
では、バスに乗せるべき人を
どのように判断すればいいのだろうか?
それが採用基準だ。
採用基準に正解はない。
あなたの会社の価値観に合う人が
採用すべき人だ。
採用のプロセスで候補者が
自社の価値観に合っているかを
慎重に見極めるしかない。
そのためにも
採用基準とそれを見極める
質問を周到に準備するのだ。
なにしろ、間違った人を採用すると
バスから降ろすには相当な負担が
かかるのはわかっているのだから。
自社に合った人材を集めることで、
より早く、目指している場所に
辿り着けるようになるだろう。
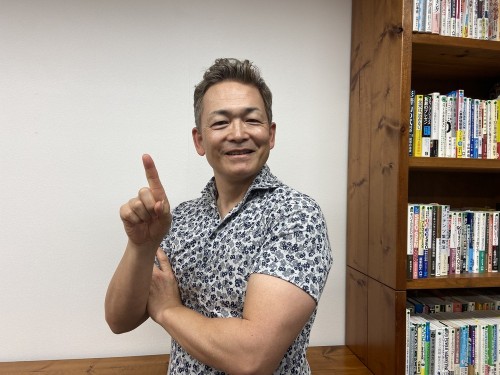
池本克之です。
僕らは、スピードを重要視します。
中には、スピードより質が大切だと
お考えの方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、どちらが正しいということはないです。
なぜなら、それは各自の価値観だからです。
私の価値観では、
スピードが重要だと考えています。
私以外にも、スピードを優先している方は
多いのではないでしょうか。
しかし、社長である私たちが
スピードを大切にしていても、
スタッフが同じ価値観とは限りません。
中には、業務が遅いと感じる方もいるでしょう。
「いつまで取り組んでいるのか」
「なぜ、それほど遅いのか」
「もっと早く進めてほしい」
と感じることがあるかもしれません。
業務が遅い方を見ると、
イライラしてしまい、
仕事がなかなか進まないため、
「自分で行ったほうが早い」
とお考えになる社長も多いでしょう。
その結果、結局ご自身で作業を
引き受けてしまうこともあるかもしれません。
しかし、この状態が続けば、
組織の成長が停滞し、
会社の発展も遅れてしまいます。
社長のストレスも軽減されません。
この状況を避けるためには、
社長の価値観をスタッフに
しっかり共有することが大切です。
私の場合は、スピードが重要だという
価値観です。
この価値観をスタッフにも伝え、
繰り返し教育します。
さらに、なぜスピードが重要なのか、
その理由を説明します。
理由を理解してもらうことで、
ただ「スピードが大事」と伝えるより、
納得して行動に移しやすくなるからです。
また、口頭だけでなく、
文書として価値観をまとめ、
スタッフに配布しています。
私は、自分の価値観をまとめた
CCS(コーポレート・カルチャー・スタンダード)を
手帳にしてスタッフへ渡しています。
CCSは、企業文化の基準を示すものです。
中小企業では、社長の価値観が
企業文化になりやすいため、
文書化して共有しています。
スタッフは困ったとき、手帳を確認すれば
正しい行動が分かります。
そのため、私に逐一質問する必要がなくなり、
私の時間も確保できます。
CCSには私の価値観が凝縮されています。
スピード以外にも、
業務で大切にしていることや、
絶対に避けるべきことなども記しています。
人は口頭での指示だけでは忘れがちですが、
文字として目に見える形なら記憶に
残りやすいものです。
私たちとスタッフの価値観は、
もともと大きく異なります。
しかし、価値観を文書化し、
繰り返し教育することで、
スタッフの価値観を私たちの価値観に
近づけることが可能です。
社長のストレスを減らし、
時間を確保するために、
この方法が最も効率的だと考えています。
PS
組織学習経営に必要なメソッドが学べる
お勧めのセミナーがあります。
以下をチェックしてください
↓
詳細はこちら
池本克之です。
生まれた時からデジタルに囲まれ、
親からスマホで情報を見せられて、
あるのが当たり前な世代。
それがデジタルネイティブだ。
そうではない世代が感じる
デジタルへのストレスを
彼らはまったく感じないのだろう。
例えば、弊社の大学生インターンは
スマホで簡単な動画編集やリサーチを
済ませてしまう。
そして、彼らは多様性を重視しながら、
自分の時間も大切にするので
効率を求める傾向が強いようだ。
特に40代以上のそれがわからない
上司がデジタルネイティブに
「言ってはいけないワード」がある。
それが
「これって当たり前だよね?」
というワードだ。
40代以上には当たり前でも、
デジタルネイティブにとっては
初めてのことがある。
それなのに「当たり前」と言われると
学ぶ意欲を削ぎ、萎縮させてしまう。
だから禁止ワードなのだ。
「当たり前」とは、
一般的に認識され、疑問を持たれることの
少ない事象や状態を指す言葉です。
とAIが教えてくれる。さらに、
社会的な常識やルール、自然の法則など、
特別な説明を必要とせず、多くの人々が
共有する認識や価値観を表します。
社会的に当たり前と思われる行為、
その他物事のこと。
彼らと知るのと同じAIが言うのだ。
デジタルネイティブと
いまだにデジタルにストレスを
感じる世代にはギャップがあるのだ。
この事実を受け止めることは
優秀な彼らの意欲を高めることにつながる。
そのためにも
言葉の選び方を意識しないといけない。
がんばれ、社長!

池本克之です。
きっと、あなたにも
このような経験があるのではないでしょうか。
自分が伝えた内容が、
スタッフに違う形で届いてしまう。
言葉と行動が一致しない。
「どうして、言った通りに動けないのか」
と感じて、
イライラしたことがあるかもしれません。
本来、求めている動きとは異なるため、
同じことを何度も伝え直す必要が生じます。
この時間はとてももったいないと感じます。
なぜ伝わらないのか。
なぜ言った通りに行動できないのか。
そう思った経験をお持ちの方は
少なくないように感じます。
同じやり取りを繰り返すのは
面倒ですし、効率も悪く、
貴重な時間がどんどん奪われます。
私たちの時間は貴重ですから、
可能な限り無駄を避けたいものです。
では、どうすればよいのでしょうか。
それは、相手に何かを伝える際に
「八割伝える努力」をすることです。
人それぞれ、価値観が異なります。
価値観が違うということは、
考え方や捉え方も
人によって異なるということです。
つまり、相手によって
伝え方を変える必要があります。
この人に伝わったからといって、
別の人にも同じ方法で伝わるとは限りません。
私は以前、コミュニケーションについて
ある方から学んだことがあります。
それは、自分の話が相手に伝わるのは
およそ七割程度だということです。
そこで、「八割伝える努力」をすると、
伝わり方が大きく変わると教わりました。
たとえば、文章で伝わりにくい方には
直接お会いして話す。
図やイラストを使うと理解しやすい方も
いらっしゃるでしょう。
このように、相手によって
伝え方を変えることが大切です。
私たちの時間は限られています。
貴重な時間を無駄にしないためにも、
伝え方を工夫することで、
イライラする時間を
減らせるのではないでしょうか。
どのような場面でも、相手を変えるより、
自分を変えるほうがはるかに簡単ですから。
池本克之です。
会社には、さまざまな人がいますので、
中には
「この人には本音が話しにくいな〜…」
と感じる相手がいるかもしれません。
それはどのような人かと言いますと、
たとえば、こちらが何かを伝えると、
すぐに否定から入る方です。
相手の意見や考えを受け止めようとせず、
(受け止めているかどうかが
分かりにくい場合もあります)
自分の考えだけを主張します。
そのような人は、どの会社にもいるかもしれません。
一度でも受け止められずに、
(あるいは、受け止められているかどうかが分からずに)
自分の考えばかりを述べられると、
「次はもう相談しない」
「この人に言っても何も変わらない」
「次はもうないだろう」
と感じるようになります。
こうして、相手が気付かないうちに
お互いの間に溝が生まれます。
さらに、思うことや感じることがあっても
言えませんので、ストレスがたまり、
相手への印象も悪いままとなるでしょう。
それでも、仕事は続けますので、
溝があるとは相手が気付かない場合もあります。
この状況では、いずれ感情が
爆発することも考えられますし、
知らない間に組織にひずみが生じる
可能性もあります。
人は、言いたいことがあっても言わない方や
言えない方もいますので、
表面上うまくいっているように見えても、
実際はそうではないことがよくあります。
それでは、
「この人には話しやすい」
と感じるのは、
どのような相手でしょうか。
それは、どのような内容でも
まずは受け止めてから、
自分の考えを伝える方だと感じています。
たとえ自分と相手の考えが異なっていても、
先に相手の言葉を受け止め、
その後で自分の意見を述べるのです。
すると、聞いている側は
最初に理解を示してもらえていますので、
違う考えを提示されても
あまり嫌な気持ちにはなりません。
「ああ、確かにそのような考えもあるかもしれない」
と受け入れやすくなります。
また、話しやすい人には、
さまざまなことを伝えたいと
思えるようになります。
困っていることや、不満に感じていること、
改善した方が良いと内心で考えていることなどを
言いやすくなるのです。
このような関係性は、
受け止めてもらえない相手と比べると、
格段に良くなるでしょう。
心理学的にも、人は自発的にアイデアを出し、
それが必要とされたり肯定されたりすると、
とても楽しい気分になるとされています。
肯定されれば嬉しいですし、
受け入れてもらえれば、
さらに嬉しいものです。
しかし、上司の中には、
部下が自分の考えを伝えたり
新しいアイデアを出した際に、
渋い顔で「でもさ〜」と言ったり、
「そんなのはくだらない」
「実現性がない」と否定する方もいるかもしれません。
また、部下の意見を最初から
軽視する方もいるでしょう。
このような状態では、人間関係がうまくいかず、
仕事も円滑に進まない可能性があります。
この状況を避けるために、
お互いが気持ちよく働けるように、
さらに、問題や不具合が生じた際に
速やかに気付き、改善できる環境を
整えるためにも、
どのようなことを言われても、
まずは受け止める姿勢を持つことが、
上司にとって非常に重要だと考えています。
池本克之です。
時間は限りある貴重な資源だ。
これは誰にでも当てはまるが、
特に、社長の時間はとても貴重だ。
それなのに、価値の低いことに
時間を使ってしまう。
いや、使わざるを得ないのだ。
例えば、
思ったとおりに動かない社員、
何度言っても伝わらないイライラ。
それをどうにかするために
説明をする、マニュアルを作る
そして、悩むことに時間を使う。
貴重な時間が奪われていき
本来やるべき重要な仕事に使う
時間が減っていく。
これでどうやって会社を
成長させればいいのだろうか?
その気持ちはよくわかる。
会社の将来を見据えて
経営をしていきたいのに
それができない。
そのストレスは大きく
その状態から抜け出せないことで
不安もつきまとうだろう。
それを解決するために原因を
知ってほしい。
それは、価値観が違うからである。
社長と社員の価値観は違うのだ。
そして、お互いの価値観が違うことで、
何度言っても伝わらないのだ。
それを解決するには、
お互いの価値観を一致させていく
以外に方法がない。
中小企業の場合、
社長の価値観がそのまま
会社の価値観に反映される。
それは当然のことだ。
だからこそ、社長の価値観を明確に
言語化することが必要だ。
そして、さらに重要なことは
それを社員に教えることだ。
なぜなら、価値観が違うと
言語化されてもその意味の解釈が
違うからだ。
言語化された価値観が意味する
ことを社員が理解し、行動できる
ようにすることを本来、教育という。
継続して教育をすることで
価値観が統一され、伝わらない
ストレスから解放される。
長い道のりではあるが、
やらなければ現状は変わらない。
やることでしか成長はない。

池本克之です。
人間ですから、誰でも緊張いたします。
私も大勢の前で話す機会が多く、
そのたびに緊張を感じております。
中には、ほとんど緊張しない方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、重要な商談や取引先への謝罪、
大勢の前でのプレゼンなど、
緊張を覚える場面は多いものです。
緊張すると、ふだんの自分とは
違う状態になりがちです。
考えていたことが話せなくなったり、
「こんなことを言うつもりではなかった」と
後悔することもあります。
自分が何を話しているのか
分からなくなるような経験を
された方もいらっしゃるでしょう。
緊張で汗が出てくる場合もあります。
このような状態では、
ここぞという場面で本来の
パフォーマンスを発揮できません。
その結果、後悔が残ってしまいます。
適度な緊張はプラスになることもありますが、
極度の緊張は自分らしさを
失わせる要因となります。
では、どうすればよいのでしょうか。
私は、その対策としてゴルフを勧めております。
ゴルフは「考える時間」が豊富なスポーツです。
プレー中に立ち止まって戦略を練る時間があり、
ボールを打つよりも考えている
時間の方が長いほどです。
人は考える時間が長いほど緊張しやすくなり、
想像が膨らむとマイナス思考に
陥ることもあります。
結果として、緊張がさらに高まる悪循環が生まれます。
しかし、この「立ち止まって考える」行為を
繰り返すことで、メンタルが鍛えられていきます。
何度も緊張する場面に直面するうちに、
慣れが生まれるからです。
緊張しにくいメンタルが身につけば、
大事な場面で実力を最大限に発揮できます。
いつもと同じ自分で、
冷静に判断できるようになるでしょう。
緊張して判断を誤り、
大切な場面でミスをしないためにも、
緊張しやすい方はゴルフでメンタルを
鍛えてみてはいかがでしょうか。
池本克之です。
仕事のできないおじさんほど
会社にとってムダなものはない。
仕事ができなくても
周りに影響を与えず
給料が安ければいい。
しかし、実態はその逆だ。
周りの仕事を増やし、ストレスを与え
それでいて優秀な若い人より給料が高い。
このムダをどうにかしないと
優秀な若い人の方が会社を辞めていく。
なぜなら、合理的ではないからだ。
ハッキリ言って、アホらしい。
このムダを放置する会社が
そう見えるのだ。
そうは言っても役職についていて
長年、貢献してくれているので
どうすればいいのか?
役職者にいかにうまく動いてもらい、
どう成果を出してもらうかは、
社長の手腕にかかっている。
例えば、大企業では役職定年が制度として
存在する場合がある。
個体差はあるもののある年齢で能力が
低下して、働かないおじさんになってしまう
ことを見越した制度とも言える。
リコーでは、ジョブ型人事制度と同時に、
2軍制度を取り入れているという。
それは、
一定の期間内に必要なスキルを習得しないと
一般職に降格するという制度だ。
実際に降格した役職者の中には、
これまでスキルアップしてこなかったが
危機感が生まれ学ぶチャンスになった。
といった、仕事に対するモチベーションが
アップしたという声があがっているという。
それなら、仕事のできるオジサンなので
何の問題もない。それどころか、戦力として
活躍の場があるということになる。
降格という刺激を受けて、スキルアップする
という反応が生まれる。
どんな刺激を与えるか?
社長の腕の見せどころだ。

池本克之です。
スタッフの中には、
残業をしたくないと考えている方も
いるかもしれません。
なるべく早く帰宅し、
自分の時間を大切に
したいと思う方もいます。
家族が待っている場合は、
早く帰って家族との時間を過ごしたいと
考える方もいるでしょう。
仕事が早めに終わったら、
ジムへ行こうと考えている方も
いるかもしれません。
仕事以外の時間が充実していれば、
その経験は仕事にも良い影響を与えます。
とはいえ、残業を減らしたいと思っても、
なかなか減らせない方もいます。
日々の業務が忙しく、
後回しになっている仕事があるためです。
そのような方は、
「今日も残らないと終わらない」と感じ、
疲れていても必死に業務を続けています。
スタッフが残業していると知った社長の中には、
「残業を減らしてほしい」
と指示する方もいるでしょう。
「どうしてそこまで遅く働く必要があるのか」
と疑問に思うこともあるかもしれません。
しかし、スタッフから見ると、
「そんなのは無理だ」
「どうやって減らせと言うのか」
と感じる場合があります。
「社長は現場を理解していない」
と受け取られ、
関係が悪化することもあります。
ただ残業を減らすよう伝えるだけでは、
問題は解決しません。
何が原因で残業が発生しているのかを
考えなければ、
根本的な解決には至らないのです。
多くの社長は日々多忙で、
スタッフとのコミュニケーションが
不足しがちです。
スタッフが今何に困り、
何に悩んでいるのかを、
じっくり話し合う時間が取りにくいのかもしれません。
そのため、目に見える状況だけで
判断してしまうこともあります。
しかし、なぜ残業が必要なのかを
把握しなければ、
残業の削減は難しいでしょう。
原因を知るには、スタッフと話す時間を
設ける必要があります。
あなたは最近、スタッフと対話する時間を
確保しているでしょうか。
ある記事には、
「職場では全員がパソコンに向かい、
キーボードの音だけが響く。
業務量が膨大で、
無駄話をする余裕がない。
毎日顔を合わせているのに、
互いに何を考え、
何を悩んでいるのかを語り合う機会がない」
と記されていました。
確かに、このような状況の
会社は多いかもしれません。
このままでは、互いの状況を把握できず、
困りごとも見えないままです。
問題があっても気付けず、
深刻化する恐れがあります。
これは好ましくありません。
社長は多忙かもしれませんが、
少しでも時間を取り、
スタッフと話すことが大切だと感じます。
そうすることで、
これまで気付かなかった課題を把握し、
残業削減のきっかけをつかめる場合があります。
単に「残業を減らせ」と伝えるだけでは、
実行は難しいものです。
もし、
「最近スタッフと話していない」
と感じるようでしたら、
ぜひ時間を確保してみてください。
それがスタッフの問題解決を早め、
業務を効率良く進めることにも
つながるでしょう。
池本克之です。
忠誠心と聞くと、
なんだか良い言葉のように感じます。
相手へ真心や誠意を、
尽くそうとする気持ちだからです。
お互いに信頼関係が築けているのであれば、
大変素晴らしいことでしょう。
しかし、この忠誠心は、
行き過ぎると良くない方向へ向かう場合があります。
例えば、会社において社長と部下、
あるいは上司と部下の関係になると、
絶対的服従に近い忠誠心を示す方が、
中には存在します。
このような場合、
上からの指示は必ず実行されます。
一見すると、理想的に思えるかもしれません。
ところが、不正や欠陥があっても
報告しないという事態が、
平然と起きるようになります。
その結果、たとえ悪いことであっても、
悪いと認識しないまま実行されます。
「ばれなければ構わない」
「〇〇さんが言うのだから正しいはずだ」
といった考え方に陥ってしまうのです。
こうなると深刻です。
やがて組織は崩壊し、
会社も長続きしなくなるでしょう。
想像するだけでも恐ろしい事態です。
本来、美徳とされる忠誠心でも、
上下関係の下では歪む可能性があります。
では、このような歪んだ忠誠心をなくすには、
どうすれば良いのでしょうか。
やはりトップの在り方次第だと感じます。
トップが誤った方向へ進めば、
部下も容易に同じ方向へ引き込まれます。
中には、社長の行動や考えを見て、
「これではいけない」と判断し、
早々に退職を選ぶ方もいるかもしれません。
人は窮地に立たされると、
痛みから逃れたいと考えます。
一刻も早く状況を避けたいとも思います。
そこで正しい判断を下す人もいれば、
自分だけ良ければ良いと考える人も現れます。
長期的に考えると、
私たち社長の行動や発言は、
部下を正しい方向にも、
間違った方向にも導く可能性があります。
忠誠心という言葉は素晴らしいですが、
部下が誤った忠誠心を抱かないように、
私たちトップに立つ者が、
正しい行動を継続することが重要だと、
強く感じております。