池本克之です。
多くの企業が、
業務の効率化や生産性の向上を目的に、
社内ルールを定めている。
働き方が多様化し、
ハイブリッドワークや副業制度が
一般化した2025年の今、
ルールの存在はますます重要視されている。
実際、私自身もマネジメントにおいて、
ただ信じて任せるだけでは
組織は動かないと考えており、
「ルールを守ること」の価値を
何度も伝えてきた。
ルールは組織を整え、
属人的な判断を防ぐための仕組みである。
だからこそ、
それに従わない行動には反応が起きる。
「なぜ、言ったとおりにやらないんだ」
「これが会社のルールだぞ」
こうした怒りや苛立ちが湧くのは
自然な反応である。
部下のルール外の行動に対し、
「こいつはダメだ」と
評価を下す上司も少なくない。
しかし一方で、
私は最近、こうも思う。
本当にルールを守ることだけが正しいのか?
ルールに従いさえすればいいという
空気が蔓延すると、
現場での創意工夫が失われる。
特に今日のように変化が激しく、
過去の成功モデルが
通用しなくなってきた時代には、
むしろルールにとらわれない
発想力と柔軟性が求められている。
たとえば、上司の意図を超えて、
現場判断で顧客対応をした部下がいたとする。
ルールから外れているかもしれない。
しかし、その行動が顧客満足を高め、
信頼につながったとしたらどうだろうか。
それを「違反」として処理するだけでは、
次のチャレンジを潰すことにもなる。
ルールが部下の挑戦を抑圧し、
生産性を逆に低下させてしまう。
こういった事例は
私のクライアント先でも少なくない。
特に中堅社員の「思考停止」が
顕著になってきているのも、
ルール偏重の副作用である。
もちろん、
コンプライアンスや法令、情報管理など、
決して逸脱してはならないルールは存在する。
そこは厳格に運用されるべきである。
しかし、日々の業務の中で、
上司の裁量や現場判断の余地がある領域まで
ルールでガチガチに縛ってしまうと、
社員の成長も、
会社の柔軟性も損なわれてしまう。
ルールを守ることは重要である。
だが「ルールの外に出るな」と
言い続けるだけでは、
部下は萎縮し、
イレギュラーに対応できない人材になってしまう。
「言われたとおりにやったのに…」
「ルール通りなのに、なぜ怒られるんですか?」
そうした部下の声が、
組織の成長の鈍化を示している。
大切なのは、ルールと信頼のバランスである。
ルールの枠を越えた部下の行動を
すぐに「違反」と決めつけるのではなく、
なぜそうしたのか、
どんな判断があったのかをまず聞く。
そしてその背景にある価値を認め、
場合によっては「よくやった」と言ってあげる。
その一言が、部下の自信を育て、
次の一歩につながる。
ルールに従うことの価値を認めつつ、
あえてルールを超える勇気をも評価すること。
それが変化の時代を
生き抜くリーダーに求められる姿勢である。
お電話かフォームにて
お気軽にお問い合わせ下さい。
皆さまからのお問い合わせ、お待ちしております。
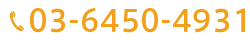
お電話受付時間:10:00~17:00