池本克之です。
会社の雰囲気というものは、
数値には表れない。
しかし、社内に一歩足を踏み入れれば、
誰もがすぐに感じ取れる。
活気があるのか、
停滞しているのか、
張りつめているのか。
最近「なんとなく雰囲気が悪い」と感じるなら、
それは社長が見逃してはいけないサインである。
ここ数年で
ビジネスの環境は厳しさを増している。
物価や人件費の上昇、
デジタル化競争の加速、
優秀な人材の流動化。
外部環境に社員が不安を抱き、
社内の空気が重くなることは珍しくない。
こうした時期にこそ、
社長は「空気を変える役割」を担わなければならない。
では、どうすればよいのか。
私は3つの視点が重要だと考えている。
第一に、
社長自身が「前を向いている姿」を示すことだ。
雰囲気は数字ではなく感情から生まれる。
社長が不安を隠さずに嘆けば、
社員はさらに萎縮する。
逆に、厳しい現状を認めつつ
「だからこそ、こう動こう」と前を向けば、
空気は確実に変わる。
リーダーの姿勢は、
組織全体にそのまま映し出されるのだ。
第二に、
社員同士の「小さな成功体験」を
共有することである。
空気が悪いとき、
人はどうしても失敗や課題ばかりに目を向ける。
そこであえて、営業が受注した小さな案件や、
お客様の感謝の声を社内で紹介する。
「できていること」に光を当てると、
社員は前向きな気持ちを取り戻す。
雰囲気を変えるには、
大きな改革ではなく小さな承認の積み重ねが効く。
第三に、
リアルな対話の場をつくることである。
リモートやデジタル化が進む中で、
人と人の距離が遠のいている。
画面越しでは空気は変えにくい。
だからこそ社長が現場に足を運び、
直接言葉を交わすことが必要だ。
もし支店がいくつかあるならば、
月に1回は足を運んで直接会う機会を作ってほしい。
面談ができたらいいが、少しの雑談でもいい。
社員は「社長が自分たちを見ている」と
感じるだけで、安心と一体感を得る。
空気を変えるには、
制度よりもスピード感が大事である。
雰囲気の悪さを放置すれば、
それは雪だるま式に広がり、
やがて優秀な人材の離脱につながる。
一方で、早い段階で火を消し、
希望を見せることができれば、
組織は立て直せる。
経営者の最大の仕事は
「会社の空気を健全に保つこと」である。
戦略や数字も重要だが、
その前に人の心がある。
心が閉じていては、
戦略も数字も動かない。
2025年下期、
経営環境はますます厳しさを増す。
だからこそ社長は、
まず自らの言葉と行動で
空気を変えていかなければならない。
会社の雰囲気を変える力は、
いつの時代も
社長自身の背中にかかっている。
お電話かフォームにて
お気軽にお問い合わせ下さい。
皆さまからのお問い合わせ、お待ちしております。
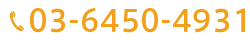
お電話受付時間:10:00~17:00