池本克之です。
2025年も終盤にさしかかっているが、
このところの日本経済を冷静に眺めると、
社長の給与判断における迷いが
生まれやすい状況にあることは確かである。
賃上げ要請は大企業を中心に連鎖的に広がり、
春闘では前年を上回る水準が常態化している。
物価上昇率は依然として2%台後半を推移し、
生活防衛意識を持つ社員から
「給与を上げてほしい」との声が
高まるのは自然な流れである。
加えて、深刻な人材不足が続き、
中堅層や専門人材は市場で
奪い合いの状態にある。
この環境下で社長に突きつけられるのは、
社員の「交渉圧力」である。
給与面での要求は
以前よりもストレートになり、
時に「強く言えば社長は折れる」
といった空気さえ醸成されている。
私が多くの経営者から給与の件で
相談された際に必ず言うことは、
「給与をごり押しで決めさせてはいけない」
この一点である。
なぜなら、
給与は経営の最重要意思決定のひとつであり、
経営者の戦略そのものだからだ。
インフレ率、
業績見通し、
資金調達環境、
そして将来の投資余力。
これらを総合的に勘案して初めて、
合理的な給与水準が導き出される。
社員の要求や感情だけで給与を動かせば、
資金繰りは不安定になり、
投資は遅れ、組織全体の方向性が揺らぐ。
加えて一度「声を荒げれば通る」
という前例をつくれば、
組織文化は瞬時に変質する。
給与は公平性が命である。
市場の相場を参考にしつつも、
社内の評価基準に基づいて
一貫した水準を設定しなければならない。
もし一部の社員だけが
社長へのごり押しで得をしたとなれば、
残る大多数の士気は確実に下がる。
結果的に離職者は増え、
経営コストはさらに膨張する。
現在の経営環境は不確実性が高い。
円安は依然として続き、
輸入コストは確実に経営を圧迫してくる。
資源価格の変動も読みにくく、
世界経済の減速リスクもある。
だからこそ、
給与決定は冷徹にデータに基づく必要がある。
たとえば
「消費者物価指数と業績成長率を加味し、
上げ幅を算定する」
「役割等級制度により
市場価値を見える化する」など、
ルール化が欠かせない。
また、給与だけで人材を引き留めるのは
限界に来ている。
2025年の労働市場では、
柔軟な働き方やキャリア開発の支援といった
非金銭的要素が大きな差別化要因となる。
つまり、給与はあくまで合理性の象徴とし、
それ以外の領域で魅力を創出していくのが
社長の役割である。
給与においては、
経営者は一切の情に流されてはならない。
給与をごり押しで決めさせてはいけない。
これは経済合理性の問題であると同時に、
経営者としての信頼を守る問題である。
揺るがない基準を持ち、
データに裏づけられた説明を続ける社長こそが、
2026年、激動の時代を生き抜くのだろうと思う。
お電話かフォームにて
お気軽にお問い合わせ下さい。
皆さまからのお問い合わせ、お待ちしております。
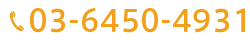
お電話受付時間:10:00~17:00