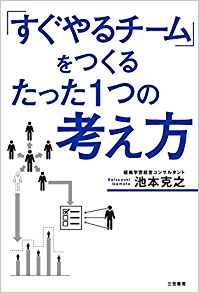池本克之です。
今は、部下を正しく叱れない上司が 増えている。
部下からの評判が下がることや 部下から嫌われることを恐れて、 叱ることができなくなっているのだ。
中には、見て見ぬふりをする 上司もいる。
さらに、本人やチームにとって プラスになるかどうかではなく、
自分の都合や不適切な温情に 判断が左右されている人もいる。
そもそも叱るというのは、 本人にとってマイナスになることを 正してあげる行為だ。
そこに自分の都合は関係ない。
人としてのマナーや礼儀も含め、 間違いは間違いとして きちんと指摘する。
マイナスの評価もきちんと伝えて、 プラスに導く。
これは、人とチームを動かす上で 欠かせないスキルの1つであり、 上司の仕事の1つでもある。
とはいえ、冒頭でも話したように 叱れなくなっている上司がいるのも 事実だ。
そこで今日は、 マイナスを指摘する時のポイントを お伝えしたい。
そのポイントというのは、 相手に何かを指摘しようとした時に
今から指摘しようとしていることは 本当に本人のためになっているのか?
ということを考える、 というものだ。
本人の成長のプラスになる指摘なのか? 自分の勝手な都合で怒っていないか?
あるいは、
【言わないことが 本当に本人のためになるのか?】
ということを自問してほしい。
そして、 本人のためになると思えば 叱ればいい。 ・・・・・・・・・・・・・ 以前、私が勤めていた ネット通販の会社で、 こんなことがあった。 営業成績のいいある社員が 何かにつけて上から目線だったのだ。 「consumer(消費者)」をもじってか、 お客様のことを「C」と呼んでみたり、 「うちは上場会社だぞ」 というような 横柄な言葉遣いをしたり。 「自分たちのほうが立場は上なんだ」 と言わんばかりの態度が目についた。 顧客目線で物事を考えようと しなかったのだ。 私はそんな彼に 非常に違和感を持った。 もちろん、注意をしたが、 最初は「意味がわかりません」 という感じだった。 それでも根気強く、 「お客様あっての売上なんだ。 どんなにすごい『売れる仕組み』を つくっても、 それだけで数字は立たない。 一番大事なのは、 お客様に欲しいと思ってもらえる 商品を提供することにある。 そこを忘れるな」 と伝えていた。 上に立つ者が 部下の間違った考え方を 正そうとしないと、 暗にそれを認めることになる。 そして、 多くの上司がそうなることで、 部下の態度は悪化し、 いずれ業績にも影響が出るように なるだろう。 もちろん、 本人のためになっていない指摘なら 怒られた人だけではなく、 他のメンバーのモチベーションまで 下げる原因になる。 しかし、 本当に本人のためになっていると 思うのなら、きちんと指摘する。 そして、正しい方向へ導いていく。 これが、結果的に チーム全体にとっても 良い影響をもたらすようになるのだ。 誰だって叱るのは嫌だし、 その人との関係性を考えると 躊躇してしまうこともあるかもしれない。 だが、間違った考え方を正さずに そのままにしていれば、 いずれそれが大きな問題に 発展してしまうこともある。 そんなことにならないためにも、 間違った考えはしつこく正す。 ぜひ、嫌われることを恐れずに、 正面から立ち向かっていってほしい。 PS 部下のマネジメントで悩んでいるのなら ここにヒントがあるだろう。 ↓ https://amzn.to/2lZZOFM